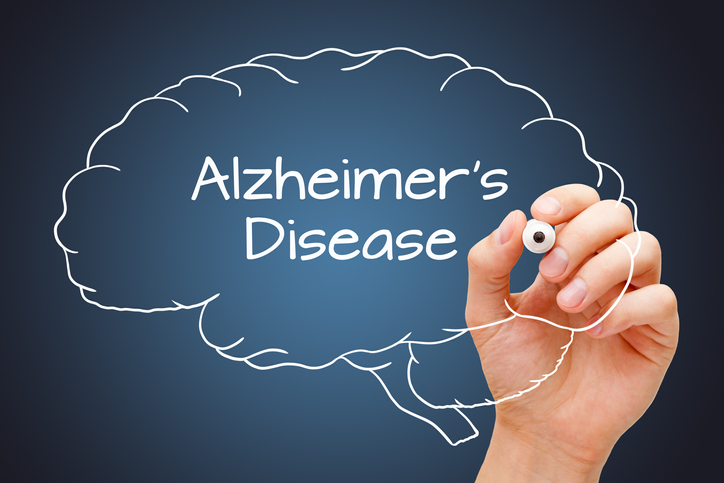自律神経失調症と認知症の関係は? 高齢者は自律神経を整えることが大事!
認知症見守り

高齢者の自律神経失調症に要注意!
季節の変わり目など、誰にでも起こる可能性がある自律神経失調症。自律神経が乱れると、さまざまな症状があらわれます。自律神経も年齢とともに変化し乱れやすくなりますが、高齢者が自律神経失調症になると、認知症につながる恐れがあるのをご存知でしょうか?
毎日をすこやかに暮らすためには自律神経を整えることが大事ですが、認知症予防の観点からも同じことがいえます。自律神経失調症の原因と症状、認知症との関係に加え、自律神経を整える方法について知っておきましょう。
自律神経失調症とは その原因と症状は
実は、自律神経失調症は特定の病名ではなく、いわゆる自律神経の乱れによる心身の不調な状態を指す言葉です。自律神経は日中や身体の活動時に活性化する交感神経と夜間や安静時に活性化する副交感神経で構成され、生きていくのに欠かせない呼吸器、消化器、循環器といった器官や内臓の働きを24時間休むことなくコントロールしています。この交感神経と副交感神経のバランスが乱れた状態が、いわゆる「自律神経失調症」です。
自律神経が乱れる原因としては、精神的なストレスや急激な温度・湿度の変化、季節の変わり目、睡眠不足や過労などによる不規則な生活、偏った食事による食生活の乱れなどがあげられます。加えて、特定の疾患や薬の副作用が影響する場合もあります。
自律神経は体全体の器官や内臓を制御しているため、そのバランスが乱れるとさまざまな症状があらわれます。例えば、頭痛、動悸、めまい、疲労感、のぼせ、下痢、便秘、関節痛などです。これらの症状は個々にみられることもあれば、複数同時にあらわれる場合もあります。
高齢者の自律神経失調症は認知症のリスクを高める?
歳をとるにしたがい、自律神経も老化し調節機能が衰えていきます。そうして起こった自律神経失調症は、認知症のリスクを高める可能性があるといわれています。
自律神経は活動時には交感神経が、リラックス時には副交感神経が交互に活性化して働きます。夜、眠っている間に副交感神経が優位に働くことで疲労を回復させ、心身の状態を整えます。睡眠の質が低下すると交感神経が活性化した状態が続くため、自律神経のバランスを乱してしまいます。
一人暮らしの高齢者は食習慣が乱れがちで、そうして起こった不規則な生活リズムが自律神経に影響を及ぼします。さらに自律神経の乱れは体の不調のみならず、認知機能、気分の低下も引き起こし、あっという間に認知症が悪化するというケースが後を絶ちません。
裏を返せば、生活リズムを整えて規則正しい食事を習慣付けていれば、脳へのよい刺激となり認知機能によい影響を与える可能性があるのです。また、運動は認知症の予防に有効とされており、自律神経を整える役割があると考えられます。質のよい睡眠をとり、規則正しい食事や適度な運動といった規則正しい生活を心掛けると自律神経を整えることができますが、それが認知症予防にもなるのです。
さらに、自律神経失調症の原因のひとつにストレスがありますが、老年期のストレスは脳に悪影響を与えます。高齢者の神経細胞はダメージに弱く、ストレスを受けると速いペースで壊れていきます。そのため、生活習慣を見直すのに加え、なるべくストレスを減らすことも大切です。
自律神経症状は認知症とどう関係する?

認知症の種類によっては、自律神経失調症に関連する症状があらわれることがあります。特にレビー小体型認知症では、自律神経症状がよく見られます。レビー小体型認知症はアルツハイマー病、血管性認知症と並ぶ三大認知症の一つであり、脳内に「レビー小体」と呼ばれる異常な構造物が多数現れることで、記憶障害をはじめとする様々な症状を引き起こします。
レビー小体型認知症の初期には、嗅覚障害や便秘、立ちくらみなどの自律神経症状に加え、レム睡眠行動障害、パーキンソン症状、幻視などもしばしばみられます。したがって、これらの症状に注意することで、早期に疾患を発見できる可能性があります。
レビー小体型認知症の方は、複数の自律神経症状を示す場合もあり、病状の進行に伴いこれらの症状も重くなります。自律神経症状は日常生活に支障をきたし、生活の質(QOL)にも影響を与えるため、早期発見と適切な対処が必要です。
ここでは、レビー小体型認知症によくみられる自律神経症状と、その対応方法を紹介します。
・起立性低血圧(立ちくらみ):立ち上がると血圧が下がり、めまいや失神を起こすことがあります。水分・塩分の補給や、ゆっくりと立ち上がることが対策となります。
・体温調節の異常:多汗や手足の冷え、寝汗などがみられます。ぬるめの入浴が効果的です。
・便秘:腸の動きが悪くなり、便秘がちになります。食物繊維の摂取や運動が有効です。
・頻尿・尿失禁:膀胱の調整がうまくいかなくなり、トイレが近くなったり失禁することがあります。薬による治療も可能ですが、副作用に注意が必要です。
自律神経失調症による転倒リスクとその予防

高齢者の転倒事故は、要介護や寝たきりなどの重篤な事態に直結するため、できるだけ避けたいものです。高齢者が転倒する主な原因のひとつが立ちくらみであり、これは自律神経失調症により引き起こされることがあります。自律神経失調症による立ちくらみは「起立性調節障害」や「起立性低血圧」と呼ばれ、子どもによくみられる一方、高齢者にも多い症状です。
ここで、自律神経の不調が高齢者に立ちくらみをもたらすメカニズムについて説明します。通常、立ち上がった際も血圧はほぼ一定で、脈拍がやや速くなる程度ですが、これは自律神経の働きで血管が収縮し、脳への血流が保たれるためです。
しかし、高齢化に伴い自律神経機能が低下すると、この調節機能が十分に働かず、立ち上がったときに血圧が大きく低下し、脈拍が大きく上昇して立ちくらみが生じることがあります。また逆に、起立時に高血圧が見られることもあります。
高齢者の場合、起立性低血圧(あるいは高血圧)が脳の血流障害に関係していることが多く、繰り返すことで脳梗塞のリスクが高まると考えられています。特に高血圧の方や降圧剤を服用している方に起こりやすい傾向があります。
自律神経失調症による立ちくらみを予防することは、転倒リスクの低減につながります。規則正しい生活リズムや自律神経の調整、寝起きや着座からの立ち上がり時にゆっくり動く習慣を身につけることで、立ちくらみを防ぎましょう。症状が気になる場合は、医療機関の受診をおすすめします。
認知症予防のためにも自律神経を整えよう
加齢によって低下した自律神経の機能を回復するのは難しいとされていますが、自律神経を整えることは可能です。ごく当たり前のことかもしれませんが、日々の生活にしっかり取り入れ、習慣化していきましょう。
・規則正しい生活リズムを保つ
毎日決まった時間に就寝・起床し、食事も一定の時間に摂るよう心がけます。朝起きて日光を浴びることが大切で、これにより体内時計がリセットされ、昼間の活動と夜間の睡眠といった規則性が形成されます。
・適度な運動
ストレッチやウォーキングなどの軽い運動から始めましょう。体を軽く動かすことで、副交感神経の働きによる疲労回復が期待できます。定期的に運動することで、疲れにくい体づくりにもつながります。
・質の良い睡眠
自律神経を整え、認知症を予防するためには、睡眠の質が重要です。質の良い睡眠を得るために、就寝前にリラックスする工夫や、寝室の環境を整えましょう。たとえば「就寝前にはスマートフォンやパソコンを見ない」「読書をする」「暗めの照明で快適な室温にする」などがあります。
・栄養バランスの良い食事
カフェインやアルコールは控えめにし、さまざまな食材からバランスよく栄養を摂ることが大切です。自律神経を整えるのに有効とされる栄養素であるビタミンやミネラルが豊富な食品を意識して摂り入れましょう。ビタミンはリンゴやミカンなどの果物に、ミネラルは野菜、果物、海藻類、乳製品、小魚などに多く含まれます。
・ストレスの軽減
趣味やリラクゼーション法を生活に取り入れましょう。スポーツや散歩、読書、音楽・映画鑑賞、アロマセラピー、昼寝など、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。
脳腸相関とは? 腸内環境と自律神経・認知機能の関係

近年、「脳腸相関」と呼ばれる、腸と脳が相互に影響し合う現象が注目されています。腸内環境の乱れが自律神経のバランスを崩し、認知機能にも悪影響を与える可能性があるのです。
人の腸内にはさまざまな菌が存在していますが、ビフィズス菌に代表される善玉菌が作り出す短鎖脂肪酸は、自律神経バランスの調整やストレス応答、消化機能の維持などに大きく寄与すると考えられています。また、腸内で生成されるセロトニンは、腸の運動を調整するだけでなく、脳にも信号を送り、気分や感情にも影響します。
国立長寿医療研究センターの研究によれば、認知症患者と健常者では腸内細菌の構成に違いが見られることが分かっています。特に便中のアンモニア濃度が高いほど認知症との関連が強く、逆に乳酸濃度が高い場合は認知症でない可能性が高まることが示されたほか、腸内細菌の代謝産物や炎症反応が脳機能や認知能力に影響を及ぼす可能性も指摘されています。
したがって、自律神経を整え認知機能を維持するには、腸内環境を良好に保つことが有効であると言えるでしょう。腸内環境を整えるためには、乳酸菌やビフィズス菌を含む発酵食品や、食物繊維が豊富な食事が推奨されます。さらに、適度な運動で腸の働きを活性化することも重要です。このような生活習慣が、自律神経の安定化や認知症予防にもつながります。
規則正しい生活を送ることで自律神経は整えられます。これは健康維持の基本であり、認知症予防にも役立ちます。高齢になっても健康的に認知症を予防しながら暮らすためには、腸内環境に良い食事と規則正しい生活リズムを心がけることが重要です。
こちらもあわせてお読みください。
▼高齢者の熱中症対策は自律神経を整えることが大事 室温にも気をつけて
▼自律神経の乱れと体温調節障害! 高齢者の大敵「季節の変わり目」に注意
▼高齢者がうまく体温調節できない理由は自律神経の乱れ? 高齢者特有の健康問題とは
▼簡易版認知症チェック!認知症の初期症状?それともただの物忘れ?
▼認知症の初期症状が出たら、要注意!
▼嗅覚の衰えは認知症の初期症状
▼認知症の初期症状が出たら、要注意!認知症予防のためには「卒酒」した方がいい?
▼ワーキングメモリーを鍛えて認知症を予防改善
▼アルツハイマー型認知症の初期症状を見逃さないために
▼アルツハイマー型認知症の予防法
▼認知症予防に効果がある脳トレ!どんなものがある?
▼高齢者と花粉症の季節 鼻炎をこじらせると認知症につながるかも?
▼熱中症が原因? 白内障リスクが4倍に? 高齢者のセンサーで見守りを
▼高齢者安否確認に欠かせない熱中症対策 センサー見守りでさらに安心
▼ヒートショックにご用心! 高齢者の安全な住まいは浴室がポイント?
▼ヒートショックの症状とは? 後期高齢者は心配? なりやすい人や予防方法など
▼ヒートショックによる突然死を防ぐために 見守りのカギはバイタルサイン
認知症見守りのおすすめ記事
-
高齢者の「安否確認」で大切なこととは? 健康・生活・孤立リスクを総合的に考える
-
ワーキングメモリとはなにか? 日常生活でワーキングメモリを鍛えることの大切さと認知症予防への期待
-
地域包括ケアシステムとは? 終の棲家で高齢者が安心して暮らすための5つの構成要素
-
2025年問題とは? 超高齢社会で現実化する老老介護・認認介護への対策は?
-
スマートホームから見守りロボットまで 高齢者の味方になる最新テクノロジーとは
-
健康のために緑茶を飲む? 国立長寿医療研究センターがカテキンと脳の健康について報告
-
コロナが周知した嗅覚障害とは QOLへの影響や認知症との関係は
-
歯周病が認知症を悪化させる? 歯周病予防と治療のポイント
-
認知症になれば必ず見当識障害が起きる? せん妄との違いと対応の仕方
-
認知症薬「レカネマブ」が保険適用に! 若年性アルツハイマーにも光明!