ヒートショックの危険性とは! 高齢者の朝風呂は良くないのか?
高齢者問題

朝風呂は本当に健康にいい? そのタイミングがカギ
朝風呂は体が温まり気分もスッキリするので、生活リズムを整えるのにぴったりの朝活といえるでしょう。
しかし、加齢によって体温調節や血圧の変化に対する反応はゆるやかになります。高齢者が朝に入浴する場合には、お湯の温度、浴室と脱衣室の環境など配慮するべき点がいくつかあり、中でも、特に大きなポイントになるのが入浴のタイミングです。
これらのポイントに配慮せず朝の入浴で体に過度な負担をかけると、ヒートショックを起こすおそれもあります。ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧や脈拍が急変し、めまいや失神、心筋梗塞・脳卒中などの健康被害が起きる現象です。特に高齢者は自律神経の働きが弱いため、入浴時に起こりやすいといわれています。
起床直後は体温が低く、血圧や脈拍も安定しないため、起きて少し時間をおいてからの入浴が安心です。まずはコップ1杯の水を飲み、軽く体を動かしましょう。
また、朝食後1〜2時間ほど経ってからの入浴は、食べたものの消化を妨げず、体が温まりやすいタイミングです。体調によっては、午前中の遅い時間や昼前に入るのもおすすめです。安全のためのポイントに気をつけて、健康的に朝風呂を楽しみましょう。
サウナや朝風呂 高齢者は要注意
近年、ブームになるほど人気のサウナ。愛好家ではなくても、冬には体を温めるためにサウナを利用するという人も多いのではないでしょうか? ただし、高齢者のサウナ利用は体への深刻なダメージを与えるという報告もあり、注意が必要です。
冬はヒートショックの危険性が高まる季節ですが、朝風呂もヒートショックを起こしやすいといわれています。寒い時期は暖かくして過ごしたいものですが、体を温めようとして間違った方法での入浴は大きな健康被害を招きかねません。高齢者のためのサウナ利用や、冬の入浴方法について考えてみましょう。
*高齢者が注意したいヒートショックの症状や、ヒートショックのリスクが高い人の特徴、ヒートショックを起こした場合の対応などを解説しています。ぜひこちらの記事もご覧ください。
▼ヒートショックの症状とは? 後期高齢者は心配? なりやすい人や予防方法など
サウナ中の救急事故の大半が高齢者!
ここ数年、多くの人がサウナを楽しむ一方でサウナ中に体調が急変し救急搬送されるケースが全国で増加しており、その多くを高齢者が占めています。
福島県郡山の広域消防組合によると、2013年から2022年までの10年間で、管轄地域内でサウナ利用中に救急搬送されたケースは101件。そのうち約70%を60歳以上が占め、サウナ中の救急事故が高齢者に集中していることがわかります。
救急搬送された人の症状として失神・意識障害が最も多く、熱中症・脱水症、脳疾患と続き、サウナ後の転倒や水浴中の溺水など深刻な事故につながったケースも少なくありません。
さらに、搬送者の半数以上に高血圧症や心疾患、動脈硬化症、糖尿病など、高齢者に多くみられる基礎疾患があり、こうした持病がある人ほどヒートショックを起こしやすいとされています。高温のサウナ室から水風呂や外気に触れる場所への移動により血圧が乱高下してヒートショックを招いたことが、これらの事故の一因となった可能性も考えられます。
高齢者はサウナを避けるべき?
高齢者にとってサウナは健康リスクが高い場所といえますが、全くサウナを利用できないというわけではありません。
高齢者でも楽しめるおすすめのサウナ浴の方法もあります。それは、60℃ほどの「低音サウナ」と呼ばれるサウナ施設の利用です。ただし、100℃近くの高温サウナと同様に無理をせず、適切な方法での利用が大切です。
●高齢者のサウナ利用のポイント
・持病がある場合は事前にかかりつけの医師に相談する
・サウナの前にはコップ2杯分の水分を摂る
・短時間での利用にとどめ、快適さを感じるくらいで出る
・サウナ室を出るときは、ゆっくり立ち上がる
・気分が悪くなったりのぼせたりしたら、すぐに出る
・サウナ後はぬるめのシャワーやかけ湯で徐々に体を冷やす
・サウナ後は十分な水分と休憩をとる
・サウナ後の水風呂は控える
サウナから出た後は水分補給をして、暖かくして少なくとも30分は休憩するようにしましょう。
また、サウナ後に無理に水風呂に入る必要はありません。水風呂に入る場合は足元から少しずつ水をかけて体を慣らしてから16℃以上の浴槽にゆっくり入り、体が冷える前に上がりましょう。
サウナに慣れている場合でも、体調次第で思わぬ事故につながることもあります。当日の体調をよく確認し、無理のない範囲で利用するようにしましょう。
血圧が大きく変動する朝の入浴にも注意を
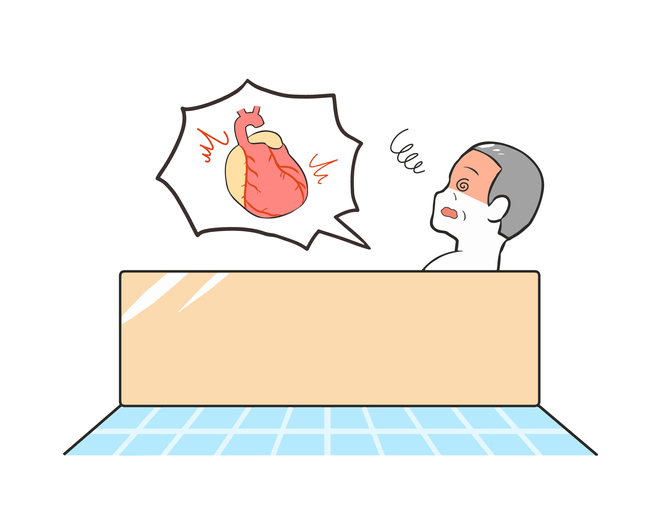
ヒートショックのリスクが高い朝の入浴も気をつける必要があります。寒い朝にはお風呂に入って体を温めて…と考える方も多いかもしれませんが、朝は血圧の変動が大きい時間帯。血圧は早朝の寝ている間から目覚める時間に向かって上昇します。しかし、目覚めたばかりでは体温が低いので、熱いお湯に触れると急激に血圧が上がってしまう場合があります。夜よりも朝の入浴の方がヒートショックのリスクが高く、特に冬の朝風呂はより一層の注意が欠かせません。
ヒートショックは体が急激な寒暖差を経験することで起こるとされています。血圧が変動しやすい時間帯に、暖かい寝床から寒い脱衣室を経てシャワーを浴びたり熱いお湯につかったりするといった行動はヒートショックのリスクを高める可能性があるため注意が必要です。
また、寝起きは体が脱水気味になっているので、そのまま入浴すると脱水症や熱中症になるおそれもあります。
これらのリスクを考え、寒い時期に入浴する際には温度差をできるだけ小さくしましょう。
浴室・脱衣室と他の居室との温度差は5℃以内が目安です。入浴前にあらかじめ浴室や脱衣室を暖めておき、季節にかかわらず十分な水分を補給してから入浴するようにしましょう。
寒い時期、暖かく過ごすためにサウナや朝風呂を活用する方が多いかもしれません。しかし、高齢者は特に気をつけたいのがサウナや朝風呂、冬場の入浴などヒートショックのリスクが伴う行動です。
ヒートショックに関する知識を身につけ、安全に入浴するようにしてください。
*こちらの記事もご参照ください。
▼高齢者と暖房器具 高齢者見守りで気になるヒートショック対策
▼高齢者に限らずヒートショック対策を! 知っておきたい暖房温度と体温調節の関係
ヒートショックに“温度のバリアフリー”の工夫を

ヒートショックは、重篤な健康被害につながる可能性があるとされており、その対策として家の中の環境を工夫することがあげられます。そのために知っておきたいのが家の中の寒暖差を減らす、「温度のバリアフリー」という考え方です。
例えば、居室は暖かいのに廊下やトイレは寒いといったような、家の中の寒暖差をできるだけなくすこともポイントのひとつです。
家全体を断熱リフォームする方法もありますが、そこまで大がかりなことをしなくてもちょっとした工夫で、温度のバリアフリー化を進められます。
●脱衣室に暖房器具を置く
脱衣室に小型の暖房器具を置くなどして浴室との温度差をなくしましょう。パネルヒーターやオイルヒーターがおすすめです。室温センサーや人感センサーで電源のオンオフができるタイプやタイマー付きのものなどもあります。
●浴室内を暖めておく
寒い浴室内で熱いお湯につかると、体への負担が大きくなります。入浴前にシャワーを出しておいたり、浴槽のフタを開けて給湯したりして入浴前に浴室を暖めておきましょう。
自律神経を整える入浴法で、ヒートショックへの対策を

ヒートショックが起きる要因として自律神経があります。交感神経と副交感神経からなる自律神経は、血管の収縮などを通じて血圧や体温を調節する役割を持っています。しかし、急激な寒暖差にさらされると、その調整機能が追いつかず血圧の変動を招きヒートショックを起こしてしまうのです。
その一方で、入浴の仕方によっては自律神経を整えることにもつながります。副交感神経の体を休める働きを引き出し、自律神経を整えることを意識した入浴法で、ヒートショック対策を講じながら安心してお風呂を楽しみましょう。
●入浴の仕方と注意点
・湯温 約40℃
・入浴時間の目安 10〜15分
・肩までゆったり浸かる全身浴
・急に立ち上がったり、寒い脱衣所で体を冷やしたりしない
・入浴前後には少量の水分をとる
・食後すぐや寝不足のとき、飲酒後の入浴は避ける
体を温めるだけでなく、自律神経のバランスを整えるためにも、こうした工夫を日常生活に取り入れましょう。周囲の方は、入浴時の声かけや室温の調整などのちょっとした気配りで高齢者の入浴環境を整えるサポートができます。温かいお風呂で、ほっとする時間を楽しんでください。
*詳しくはこちらの記事をお読みください。
▼ヒートショックと自律神経の関係 副交感神経を刺激する正しい入浴方法とは
▼バイタルサインとは何? 在宅介護に役立つ知識と測定スキル
▼ヒートショックによる突然死を防ぐために 見守りのカギはバイタルサイン
▼ヒートショックや転倒は交通事故より怖い?リフォームと高齢者安否確認
▼高齢者施設の暖房設定温度はどれくらい? 寒さ対策は?
▼ヒートショックの症状とは? 後期高齢者は心配? なりやすい人や予防方法など
▼ヒートショックや新型コロナ感染症 冬に備えて高齢者安否確認の強化を
▼高齢者と暖房器具 高齢者見守りで気になるヒートショック対策
▼暖房に注意して高齢者の一人暮らしを安全に
▼高齢者が注意するべき冬の健康トラブルとは
▼ヒートショックにご用心! 高齢者の安全な住まいは浴室がポイント?
この記事は2023年12月27日に新規作成し2025年10月31日に更新したものです。
高齢者問題のおすすめ記事
-
高齢者の「安否確認」で大切なこととは? 健康・生活・孤立リスクを総合的に考える
-
インフルエンザ流行に備える 高齢者が特に注意するべき症状のサインとは
-
看取りと孤独死の現実 高齢者が安心して最期を迎えるために必要なこと
-
高齢者におすすめの水分補給 熱中症対策と栄養補給について考える
-
高齢者の熱中症は重症化しやすい!? 謎の発熱、うつ熱に気をつけて
-
高齢者の一人暮らしへの自治体の支援、どんなものがある?
-
後期高齢者医療を考える。認知症で高額療養費、自立支援医療制度は使える?
-
一人暮らしは寂しい? 生きがいと認知症予防になる活動を
-
自律神経の乱れと体温調節障害! 高齢者の大敵「季節の変わり目」に注意
-
高齢者施設の暖房設定温度はどれくらい? 寒さ対策は?





















