高齢者の孤独死が増加? 原因と対策を考える
安否確認

高齢化と高齢者の孤独死
少子高齢化が続くわが国では、これに伴う様々な問題が生じています。
そのなかでも特に深刻といえるのが孤独死の問題でしょう。
孤独死は誰にも看取られることなく亡くなり、死後発見されるケースをいいます。
孤独死はどの世代の人にも起きる可能性があるものの、近年、孤独死した人のうち65歳以上の高齢者の占める割合が増え続けています。
その背景として考えられるのが、高齢者の単身世帯の増加と社会や地域からの孤立です。
同じ一人暮らしでも、高齢者は他の世代に比べて孤独死のリスクが高いことがわかっています。今後も高齢単身世帯は増加の一途をたどる見込みで、何も対策をしなければ高齢者の孤独死はこれからも増えていくことが予想されます。
高齢者の孤独死の現状や背景について説明し、国や自治体による対策や家族で行えるソリューションをご紹介します。
孤独死の定義と増加し続ける現状
まず、孤独死とはどのようなケースを指すのでしょうか?
実は、言葉としての明確な定義はありませんが、内閣府の「高齢者の日常生活に関する意識調査」では、孤独死あるいは孤立死を「誰にも看取られることなく亡くなったあとに発見される死」と定義しています。
これに加えて「自宅で死亡し、死後2日以上経過」していることを要件にすることも多いようです。
近年の高齢者の孤独死をとりまく状況ですが、ニッセイ基礎研究所の調査によると、都市再生機構が運営管理する全国の賃貸住宅での孤独死者数に占める高齢者の割合は1999年にはおよそ45%だったものが、2009年には71%近くにまで達しています。1999年から2009年の10年間での孤独死者数は全体で207人から665人と約3倍に増えており、このうち高齢者は94人から472人と約5倍以上となっているのです。
大都市である東京都23区内でも高齢者の孤独死者数は増えており、2015年の3116人から2020年の4207人と5年間で1000人以上も増えていることがわかります。
このようなことから、高齢化に比例して高齢者の孤独死が増えていることがわかります。
背景は高齢単身世帯の増加と孤立

高齢者の孤独死増加の背景として考えられるのが高齢単身世帯の増加です。
「平成30年高齢社会白書」によると、この20年ほどの間に独居の65歳以上の高齢者は10倍まで増えました。
総務省の推計では、2040年には単身世帯は全体の40%近くに達する見込みです。
ニッセイ基礎研究所は2014年時点での全国の孤独死者数を約3万人と推計していますが、単身世帯の増加により、今後いっそう多くの高齢者が孤独のうちに亡くなることが予想されます。
とはいえ、単に一人暮らしだけが孤独死の原因として考えられるわけではありません。もうひとつの大きな要因となっているのが「孤立」です。
ここ数年、孤独死の問題はマスメディアなどでもとりあげられることが多くなりましたが、内閣府の「令和2年高齢社会白書」によると、60歳以上で一人暮らしをしている人の半数以上が孤独死を身近な問題としてとらえています。
一人暮らしに孤独死のリスクが伴うのは、同居人がいないために急な病気や事故で倒れたときに助けを呼べなかったり、発見が遅れることが多いからです。
そうしたケースを避けるためにも、近隣で助け合える環境が重要になります。
しかしながら「平成28年版厚生労働白書」では、近隣の人たちと「親しくつきあっている」高齢者は1988年には64%を超えていたのに対し、2014年には32%足らずとなっていました。
一人暮らしをする高齢者の半数以上が孤独死に関する不安を抱えながら、身近に親しくつきあえる人がいないケースが多いことがうかがえます。
孤独死を未然に防ぐ 自治体の対策と家族にできること
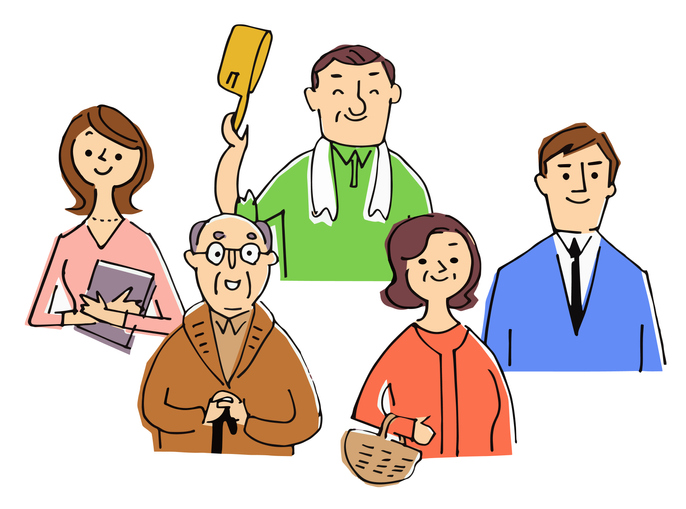
単身者が地域社会で孤立することは、孤独死のリスクにつながります。
そこで、国としては孤独・孤立対策担当室を設けて、官民協力しての取り組みを各自治体で進めています。
地域で行われている孤立対策の取り組みは自治体により異なります。
例えば、東京都足立区は「あんしんネットワーク事業」を行っています。これは、地元住民の「あんしん協力員」や地元の商店街・消防署・郵便局・配食業者などの「あんしん協力機関」が地域の高齢者を見守り、問題を抱える人を発見したら地域包括支援センターに連絡するというものです。
また、一人暮らしの高齢者の安否確認を兼ねた食事会なども各地に広がっています。
このように、高齢者を孤立させないための社会参加をうながす施策や安否確認などのサービスが全国で提供されていますが、内容は地域によって異なりますので、詳しくは地元自治体の窓口でご確認ください。
こうした自治体の取り組みに加え、孤独死を未然に防ぐために離れて暮らす家族ができる対策もあります。
そのひとつが、ITによる見守りシステムの活用です。
例えば、複合センサーを搭載した「いまイルモ」なら、離れて暮らす高齢の家族を24時間見守ることが可能です。
見守る側は、いつでもどこからでもスマホやパソコンで見守り対象者の様子をチェックすることができます。
また、「いまイルモ」はカメラと違いセンサーによる見守りなので、見守られる側としては必要以上にプライバシーに立ち入られる不安はなく、見守られている安心感を得られるでしょう。
高齢者の孤独死を防ぐためには、急な異変をいち早く発見することが欠かせません。
プライバシーにも配慮された見守りシステムで、大切な人の不安を減らしてみませんか。
安否確認のおすすめ記事
-
看取りと孤独死の現実 高齢者が安心して最期を迎えるために必要なこと
-
スマートホームから見守りロボットまで 高齢者の味方になる最新テクノロジーとは
-
小規模多機能型居宅介護とはどんなもの? 介護報酬改定の影響は?
-
孤独死の主な原因と対策とは? 亡くなってから発見まで平均18日という現状
-
スマートシティとは? 介護のDX推進とデジタル田園都市国家構想の未来
-
熱中症が原因? 白内障リスクが4倍に? 暑さを感じにくい高齢者、センサーで見守りを
-
豪雪で高まるヒートショックの危険性 血圧などバイタルサインの異常に注意
-
年末年始の帰省で、高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法の対策を話し合おう
-
ヒートショックによる突然死を防ぐために 見守りのカギはバイタルサイン
-
QOLと介助 自分のことは自分でしたい サ高住での理想的老後と自己実現




















