高齢者安否確認を考える 火災による死者の70%が高齢者
安否確認

火災の被害に会う高齢者が増えている?
安全に暮らしていくためにはいろいろな災害や事故に気をつける必要がありますが、寒い時期になってくると気をつけたいのが火災です。
最近は、国の内外で異常気象による強風や乾燥で火災が大規模化したというニュースを耳にします。火災予防にはくれぐれも注意していきたいところですが、そんな中、気になる統計データがあります。
消防庁の発表によると、2016年の住宅火災による死者の約70%を65歳以上の高齢者が占めているのです。これはショッキングな数字ですが、実はその一方で、年間の住宅火災による全体の死者数は減る傾向にあります。2007年の時点では、住宅火災による死者のうち高齢者の占める割合が約60%だったことからも、高齢者が火災の犠牲になる割合が増えていることがわかります。
これには高齢化による高齢者人口の増加が背景にありますが、ではなぜ高齢者は火災の犠牲になることが多いのでしょうか?
それは、高齢者は避難に時間がかかることが多く、就寝中に発生した火事に気づかずに逃げ遅れてしまうためです。これを踏まえた上で、高齢者を火災から守るためのポイントを知っておきましょう。
最近は、国の内外で異常気象による強風や乾燥で火災が大規模化したというニュースを耳にします。火災予防にはくれぐれも注意していきたいところですが、そんな中、気になる統計データがあります。
消防庁の発表によると、2016年の住宅火災による死者の約70%を65歳以上の高齢者が占めているのです。これはショッキングな数字ですが、実はその一方で、年間の住宅火災による全体の死者数は減る傾向にあります。2007年の時点では、住宅火災による死者のうち高齢者の占める割合が約60%だったことからも、高齢者が火災の犠牲になる割合が増えていることがわかります。
これには高齢化による高齢者人口の増加が背景にありますが、ではなぜ高齢者は火災の犠牲になることが多いのでしょうか?
それは、高齢者は避難に時間がかかることが多く、就寝中に発生した火事に気づかずに逃げ遅れてしまうためです。これを踏まえた上で、高齢者を火災から守るためのポイントを知っておきましょう。
高齢者を火災から守るために大切なこと
火災の犠牲になることを防ぐために、まず大切なことは、避難ができるように火災の発生をできるだけ「早く知る」ことです。これに加えて、火を「早く消す」「火を拡大させない」ことがポイントになります。
それでは、これらのポイントについて、実際にどうすればいいのかを見ていきましょう。
・早く知る
火災の発生をすぐに知りスムーズに避難できるように、法律により「住宅用火災警報器」の設置が義務化されています。住宅用火災警報器があれば、火災が発生した場合、就寝中でもわかるように大きな音で知らせてくれます。住宅内の設置場所は都道府県により異なりますが、避難に時間がかかりやすい高齢者のいる世帯、特に単身高齢者の世帯には必ず設置しましょう。
設置場所やどこで購入や設置依頼をすればいいかわからない場合は、消防署や役所に相談してください。また、設置していても住宅用火災警報器の電池には寿命があります。定期的に作動確認と電池の交換をしましょう。
・早く消す
万一、火災が発生しても初期のうちに消火し被害をできるだけ小さくするために、消化器を備えておきましょう。消化器といえば、大きく重いイメージがあり、お宅によっては置く場所がなかったり、「重くてうまく使えないかも」という不安のある人も少なくありません。そんな場合におすすめなのが、通常の消化器よりも軽くて小さい「住宅用消化器」やスプレータイプの「エアゾール式消火具」です。特にスプレータイプの消火具は高齢者や女性でも手軽に扱えます。
こうした消化器や消火具はホームセンターなどで購入できるので、使いやすそうなものや、使い方を確認したうえで選びましょう。また、消化器・消火具にも使用期限があるので、期限が過ぎたものは交換するようにします。
・火を拡大させない
喫煙中や調理中など、着ている衣類に引火する着衣着火により高齢者が亡くなるケースも多くみられます。このような被害を減らすために、エプロンやパジャマなどの衣類、枕・布団カバーなどの寝具類、カーテン・カーペットなどには「防炎品」を使いましょう。防炎品とは燃えにくい防炎性能を持たせたもので、火災が起きても燃え広がるのを遅らせることができます。該当する製品には「防炎製品ラベル」が明示されています。
それでは、これらのポイントについて、実際にどうすればいいのかを見ていきましょう。
・早く知る
火災の発生をすぐに知りスムーズに避難できるように、法律により「住宅用火災警報器」の設置が義務化されています。住宅用火災警報器があれば、火災が発生した場合、就寝中でもわかるように大きな音で知らせてくれます。住宅内の設置場所は都道府県により異なりますが、避難に時間がかかりやすい高齢者のいる世帯、特に単身高齢者の世帯には必ず設置しましょう。
設置場所やどこで購入や設置依頼をすればいいかわからない場合は、消防署や役所に相談してください。また、設置していても住宅用火災警報器の電池には寿命があります。定期的に作動確認と電池の交換をしましょう。
・早く消す
万一、火災が発生しても初期のうちに消火し被害をできるだけ小さくするために、消化器を備えておきましょう。消化器といえば、大きく重いイメージがあり、お宅によっては置く場所がなかったり、「重くてうまく使えないかも」という不安のある人も少なくありません。そんな場合におすすめなのが、通常の消化器よりも軽くて小さい「住宅用消化器」やスプレータイプの「エアゾール式消火具」です。特にスプレータイプの消火具は高齢者や女性でも手軽に扱えます。
こうした消化器や消火具はホームセンターなどで購入できるので、使いやすそうなものや、使い方を確認したうえで選びましょう。また、消化器・消火具にも使用期限があるので、期限が過ぎたものは交換するようにします。
・火を拡大させない
喫煙中や調理中など、着ている衣類に引火する着衣着火により高齢者が亡くなるケースも多くみられます。このような被害を減らすために、エプロンやパジャマなどの衣類、枕・布団カバーなどの寝具類、カーテン・カーペットなどには「防炎品」を使いましょう。防炎品とは燃えにくい防炎性能を持たせたもので、火災が起きても燃え広がるのを遅らせることができます。該当する製品には「防炎製品ラベル」が明示されています。
住宅防火 いのちを守る7つのポイントとは
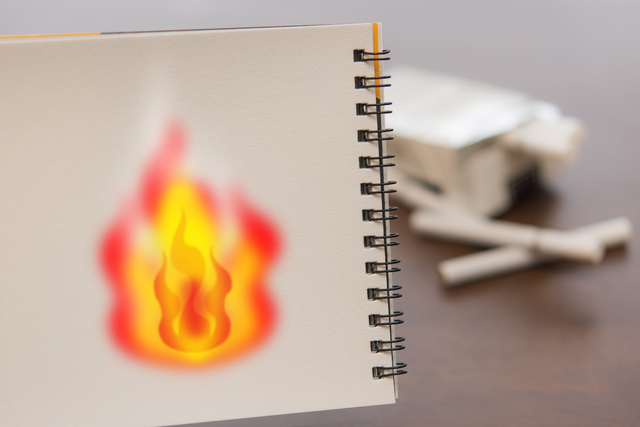
以上に加えて、火災が起きないようにすることも当然ながら重要です。火災を防止し、万一発生しても被害を最小限に食い止めるために注意したいことを消防庁では7つのポイントとして提唱しています。この7つのポイントは、次の通り、火災の原因を抑える「3つの習慣」と火災への対応策としての「4つの対策」からなります。
<3つの習慣>
・寝たばこは、絶対にやめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離して使う。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
<4つの対策>
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消化器などを設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
(消防庁 報道資料より)
<3つの習慣>
・寝たばこは、絶対にやめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離して使う。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
<4つの対策>
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消化器などを設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
(消防庁 報道資料より)
もしものときのために、高齢者安否確認の体制をつくっておこう
この4つの対策のうちの1つ、隣近所の協力体制ですが、特に一人暮らしの高齢者を守るためには非常に大切です。
また、その基本になるのが安否確認の体制です。離れて暮らす高齢の家族がいるなら、上述のような備えをした上で、高齢者本人の居宅の隣近所の方たちとコミュニケーションを取っておきましょう。異常があった場合は、知らせてもらう・本人に避難を促してもらうといった体制をつくっておきたいものです。
さらに、このような人的な体制にプラスしたいのが、ITによる高齢者安否確認のシステムです。近年では、センサーやカメラで高齢者を24時間そっと見守ることができるシステム製品が登場しています。
そのうちの1つ「いまイルモ」は、多機能センサーの端末を見守られる人の居室に設置することで、人の動きや居室の温度・湿度などをモニタリングし、そのデータをインターネットを通して見守る人のパソコンやスマホに送信します。現在の状況を随時確認でき、あらかじめ設定した時間内で人感センサーの反応がなくなった場合は、見守る側の人に自動的にお知らせメールを送信する安否確認通知機能もあるため、異変を早期に気づくことができます。
こうした「いまイルモ」と隣近所の人的な協力体制を組み合わせると、理想的な高齢者安否確認の体制になるのではないでしょうか。「いまイルモ」で異変を検知したら、すぐに近隣の方に電話やメールで連絡し様子を見に行ってもらうといったことができますね。このように様々な手段を活用して安否確認の体制づくりをすることが重要です。
火災は起きないに越したことはありませんが、起こさないという意識も大事です。
以上を参考に、大切な家族を守るためにしっかりと火災予防と対策を行っていただければと思います。
▼高齢者安否確認、自治体の取り組み
▼高齢者安否確認、民間の取り組み
▼世界の高齢者安否確認
▼災害時の高齢者安否確認
▼高齢者安否確認、プライバシーにも配慮
▼高齢者安否確認とJアラート
▼独居老人だけじゃない! 安否確認システムが守る!
▼高齢者の安否確認宅配業者と自治体がコラボ
▼高齢者安否確認 火災による死者の7割が高齢者
▼自助と共助が決め手? 災害時の高齢者安否確認
▼高齢者安否確認に欠かせない熱中症対策センサー
▼老人ホームとサ高住の違い 安否確認の視点で考える
▼高齢者安否確認見守りロボットへの期待
▼ICTを活用した単身高齢者あんしん見守り(福岡市)
また、その基本になるのが安否確認の体制です。離れて暮らす高齢の家族がいるなら、上述のような備えをした上で、高齢者本人の居宅の隣近所の方たちとコミュニケーションを取っておきましょう。異常があった場合は、知らせてもらう・本人に避難を促してもらうといった体制をつくっておきたいものです。
さらに、このような人的な体制にプラスしたいのが、ITによる高齢者安否確認のシステムです。近年では、センサーやカメラで高齢者を24時間そっと見守ることができるシステム製品が登場しています。
そのうちの1つ「いまイルモ」は、多機能センサーの端末を見守られる人の居室に設置することで、人の動きや居室の温度・湿度などをモニタリングし、そのデータをインターネットを通して見守る人のパソコンやスマホに送信します。現在の状況を随時確認でき、あらかじめ設定した時間内で人感センサーの反応がなくなった場合は、見守る側の人に自動的にお知らせメールを送信する安否確認通知機能もあるため、異変を早期に気づくことができます。
こうした「いまイルモ」と隣近所の人的な協力体制を組み合わせると、理想的な高齢者安否確認の体制になるのではないでしょうか。「いまイルモ」で異変を検知したら、すぐに近隣の方に電話やメールで連絡し様子を見に行ってもらうといったことができますね。このように様々な手段を活用して安否確認の体制づくりをすることが重要です。
火災は起きないに越したことはありませんが、起こさないという意識も大事です。
以上を参考に、大切な家族を守るためにしっかりと火災予防と対策を行っていただければと思います。
▼高齢者安否確認、自治体の取り組み
▼高齢者安否確認、民間の取り組み
▼世界の高齢者安否確認
▼災害時の高齢者安否確認
▼高齢者安否確認、プライバシーにも配慮
▼高齢者安否確認とJアラート
▼独居老人だけじゃない! 安否確認システムが守る!
▼高齢者の安否確認宅配業者と自治体がコラボ
▼高齢者安否確認 火災による死者の7割が高齢者
▼自助と共助が決め手? 災害時の高齢者安否確認
▼高齢者安否確認に欠かせない熱中症対策センサー
▼老人ホームとサ高住の違い 安否確認の視点で考える
▼高齢者安否確認見守りロボットへの期待
▼ICTを活用した単身高齢者あんしん見守り(福岡市)
安否確認のおすすめ記事
-
看取りと孤独死の現実 高齢者が安心して最期を迎えるために必要なこと
-
スマートホームから見守りロボットまで 高齢者の味方になる最新テクノロジーとは
-
小規模多機能型居宅介護とはどんなもの? 介護報酬改定の影響は?
-
孤独死の主な原因と対策とは? 亡くなってから発見まで平均18日という現状
-
スマートシティとは? 介護のDX推進とデジタル田園都市国家構想の未来
-
熱中症が原因? 白内障リスクが4倍に? 暑さを感じにくい高齢者、センサーで見守りを
-
高齢者の孤独死が増加? 原因と対策を考える
-
豪雪で高まるヒートショックの危険性 血圧などバイタルサインの異常に注意
-
年末年始の帰省で、高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法の対策を話し合おう
-
ヒートショックによる突然死を防ぐために 見守りのカギはバイタルサイン




















